今日は図書館の日。
10月に来た当初。図書は大まかに分類されて棚に並んでいたが、分類番号はバラバラで
とてもじゃないけれど、資料を探すのは困難な状態だった。
それを、11月いっぱいかけて並べ替え、分類の表示などを整えた。
これでようやく検索した資料を探し出すことができるようになった。
これをいい機会に、生徒たちにも分類ラベルを意識してもらうと、本を元に戻す時に迷わなくてすむようになるだろう。と期待する。
さて並べ替えてみると、分類番号の下の著者の表示が「ABC」と「アイウ」が混在していて、とても整理しにくい状態になっていることがわかった。
という訳で、次はこのラベルを張り替えて、表示を統一する作業に挑戦。
それとは別に、数年前に購入したと思われる本のほとんどが、カバーをはがされて、裸の状態で書架に並んでいる。「ハリーポッター」や「指輪物語」のカバーがないので、まったくもって可愛げがない本になっているのです。「あさきゆめみし」の大きな本もカバーがないので、かなり魅力に欠けている。
「カバーないのかしら?」「これじゃ、読みたいと思わないよね~」と、元からいるボランティアさんにぼやいてみたら、「カバー!第2図書室の段ボール箱にいっぱい入ってました!」と運んできた。
あるある・・・ステキなカバーがそっくり残ってる。
という訳で、ラベルの貼り代えの前に、カバーをつけて、「ブッカー」を貼る装備をすることにした。
時間も手間もかかるけれど、なんだか古ぼけて手に取ってもらえなさそうな本が、まるで新着本のようにきれいになっちゃった。
目立つところに、ディスプレイしておこう。誰かが手に取ってくれるといいなぁ。
初めての授業だ。
まず最初に、生徒たちと顔合わせ。
1年生は女子2名男子1名の3人。今日は様子を見るということで、主任の先生が、導入をしてくださった。
来年度の調理実習で、何を作りたいか?自分で考え、そのレシピをインターネットで見つける。
「お好み焼き」「ピザ」「シュウマイ」などというレシピが出てくる。
でも、それを印刷したら、もう終わっちゃうしね。
そこで、冬休みの予定表を兼ねて、カレンダー作りを提案。
今まで遣ったことのないエクセルを使って、簡単に見本を作って見る。
エクセルの基本操作を説明しながら、それぞれのカレンダー作り。
時間が足りなくて、最後までできなかったけれど、続きは来年度に引き継げそうな感じになった。
1年生は、何とか授業ができそうだ。
金曜日の2年生は手ごわい(言うことをきいてもらえない?)とわれるのだけれど・・・
どうかな?同じように、カレンダー作りに挑戦してもらおうかな?
さて明日は木曜日。中学校図書館の司書の日。
こっちは、ボランティアさんや、先生たちともいい感じになれて、仕事はしやすくなってきた。
「本に囲まれた生活」は私に合っているらしい。
書架の整理も一段落して、資料の整備をしながら、細かい配置を直したりしている。
明日は何をしようかなぁ~なんて考えているのが、楽しくなってきた。
ええ!!??
前の職場から電話がかかってきた。とある教室の中学生対象のPCの授業だそうだ。
担当の先生が病欠になったため、急遽ピンチヒッターでお声がかかったらしい。
「私で大丈夫でしょうか???」
「大丈夫ですよ。職員にPCを教えていたんですから・・・インターネットとワードとエクセルくらい見てもらえれば・・・」
ふーむ、まあ中学生だしね。興味を持たせて、導入すればいいのか?カリキュラムとかテキストはあるのかしら???
という訳で、面接?打ち合わせに行ってまいりました。
水曜日に1年生・金曜日に2年と3年。3つの授業を持つ。ただし少人数なので、ほとんど個別指導になる感じだ。
まあ、たってのご指名なので受けることにする。
顔合わせを兼ねて、明日から出勤。
さーて、生徒たちのPCのレベルはどれくらいかな?今まで、どんな授業をしてたんだろう?
どんなことをしたら、興味を持ってくれるかな?
年賀状作りはもう終わったって言ってたし・・・
来年のカレンダーでも作ろうか?
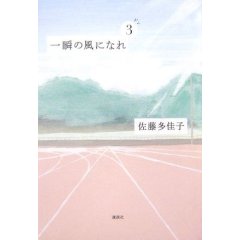 著者:佐藤多佳子
著者:佐藤多佳子
出版:講談社
初版:2006.10.24.
紹介:陸上部で短距離走をする高校生が主人公。1・2も図書館で予約したのだが、後から予約した3が先に来てしまった。でも、気になるので読んでしまいました。
かなり良かったです。恋の行方やインターハイなど、まだこの先にいろんな思いが膨らむし、希望を感じさせる。たぶん、1・2でいろんな試練があって、3なんだろうな・・・なんだか、クリスマスケーキのイチゴだけ最初に食べちゃって、土台のケーキが残っちゃった感じもするけど、まあ、イチゴだけ、また乗せればいいか・・・(訳わかんない?)
というわけで、1・2が楽しみです。
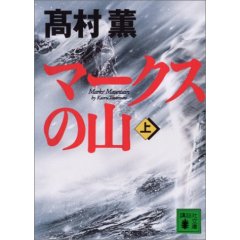 著者:高村薫
著者:高村薫
出版:講談社文庫
初版:2003.01.24.
柴門ふみさん「おいしい読書」に紹介されていたので、チャレンジした長編作。久々に読み応えのある作品で、なかなか面白かった。殺人者マークスのような人が、隣にいるかもしれないという恐ろしさもあるが、社会の裏側に隠れている組織や見えない圧力がまた恐ろしい。
そして・・・この後、捜査に関係した刑事や、木原・林原は、いったいどうなって行くんだろう。
そういえば、合田刑事って「レディ・ジョーカー」に出てきたっけ?あれ?記憶違い?
気になる・・・
スーパーエッシャー展を見に行ってきました。
私は、エッシャーの数学的な作品が大好きで、20数年前にもエッシャー展を見に行ったことがあります。
今回は、エッシャーの作品がデジタル化され、CGで動かして見れるので、また更に面白く、フシギ世界が満載です。そうそう、NintenndoDSliteを無料で貸し出ししてくれて、DSの画面と音声で作品の開設を見ることができます。これがまた便利でした。
平日の午前中で、ゆっくりと楽しむことができてよかったです。
カレンダーを買ってきちゃった。どこにかけようかなぁ?
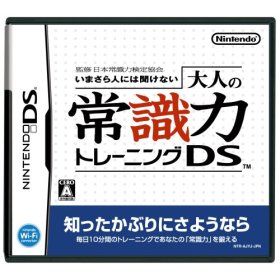 これにはまっている。自分ではまあまあ常識のあるほうだと思っていたのだけれども、娘や息子たちの方がポイントが高いので、ちょっとショックだったりする(笑)。
これにはまっている。自分ではまあまあ常識のあるほうだと思っていたのだけれども、娘や息子たちの方がポイントが高いので、ちょっとショックだったりする(笑)。
礼儀だとか、作法だとか日常はいいのだけれど、決まりとか、社会なんかが苦手分野みたいだ。
新聞やニュースをもっと意識してみたり聞いたりしないとダメだなぁ。
「脳トレ」も、20代でそれ以上若返らないし・・・といいつつ、さぼっていたのだが
もしかしたら、50代くらい成長??しちゃってたらどうしよう?
しかし、任天堂DSのソフトって、漢検にしても、ちょっと大人の心をくすぐるソフトが多いなぁ。
トランプ手品のソフトもあったしねぇ。トランプもセットで売れるわけだし・・・
すごい!任天堂。
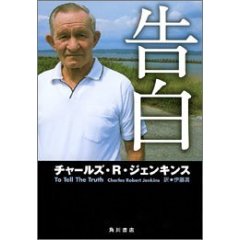 著者:チャールズ・R・ジェンキンス
著者:チャールズ・R・ジェンキンス
出版:角川書店
初版:2005.10.15.
紹介:北朝鮮に拉致された曽我ひとみさんと結婚したジェンキンス氏による、手記。
幼い頃の記憶から、軍隊に志願するまで。韓国に駐留してから、その厳しさに逃亡を企てる。しかし、その逃亡先は、軍隊よりも厳しく拘束された檻のようなところだった。アメリカ脱走兵として、利用される立場。曽我ひとみさんとの出会いと、結婚し、二人の娘を持つ。北朝鮮に暮らし、その教育を受けながらも、心はアメリカ人であり、日本人であり続けたふたり。情報の制限・正しいことを知らされずに過ごした日々。
そして運命の日がやってきた。
予測不可能な国・北朝鮮での、長い拘束生活の一端がうかがわれる。
アンコールワットから、「メジロの水浴び」に変えました。
これは、実家の父が庭に遊びに来ていたメジロを偶然撮影したもの
「これ、合成写真?」とおもってしまうほど、すごい映像です。
ところが、本当に、7羽のメジロが水庭に集まってきたんですね。正面のふわふわと丸く膨らんだメジロとそのパッチリとした目。飛び散る水しぶき!
こんな写真、狙っても、撮れるものではないなぁ~
ほのぼのと、優しい気持ちになってくるいい写真でしょう?

しばらくまえから、電気釜のふたの隙間から蒸気が出ているので気にはなっていたのだけれど・・・とうとう蓋が壊れてしまった・・・
閉めたはずのふたが、「ぱか!」っとあいてしまう。
もしも、朝タイマーを掛けて炊飯中に蓋が開いてしまったら・・・
それは大変!!!
大急ぎで、炊飯器を買いに行きました。
しかし・・・うちの炊飯器、3年くらいで壊れちゃうなぁ。
以前使っていた、ガス炊飯器はだいぶ長いこと使って、途中で内釜を買い換えたくらいだったのに・・・電気釜って、弱いのかな?それとも、使い方が荒っぽいとか???
確かに、一台目は釜に水を入れたまま移動させたりしたので、電気系統に水が入った恐れはある。だから、2台目はそうならないように気をつけてたのに・・・蓋が壊れちゃうなんて・・・
普通、電気炊飯器ってどれくらいで買い換えるんだろう??
ちなみに、我が家は朝と夜の一日2回ご飯を炊いているんだけど・・・
