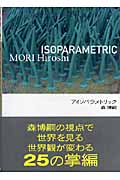 著者:森博嗣
著者:森博嗣
出版:講談社文庫
初版:2006.03.15.
紹介:「今夜から毎晩一作ずつ超短編を書きなさい」という天恵を受けた。とそれが本当かどうかは別にして、画面をスクロールせずに済む量だというから、正に1ページで話は終わってしまう。その話に、ほとんど無関係な写真とタイトルがくっついている。それなのに、その写真の一枚一枚になぜか、不思議と惹きつけられるのである。なんと言うか、森博嗣ワールドに、にやりとさせられてしまう。
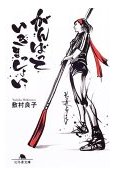 著者:敷村良子
著者:敷村良子
出版:幻冬舎文庫
初版:2005.06.10.
紹介:何とか進学校に入学したが、勉強は今ひとつ。
家では「受験勉強・地元国立大」といわれ、姉と成績を比べられ、本当に自分のやりたいことが見つからない。そんな悦子は部員を捜し「女子ボート部」を設立。そこに自分の居場所を見つける。幼なじみと・憧れの人。突然の腰痛と貧血。人生なかなか思うようには進まない。挫折と焦り。懐かしい高校時代を思い出す。
作者は私と3歳違いでほぼ同年代だ。そして、私の高校にも珍しくボート部があり、近くの江戸川でボートに乗せてもらったことがあるのだった。川下に向かっていくつもの鉄橋や道路の下をくぐって東京湾に出る。未体験の出来事にドキドキワクワクした。何より、水面がすぐ手の届くところにあるのだ。と、そこまでは良いのだが、そこで方向転換をして今度は川を遡らなければ学校まで帰れない。行きはよいよい帰りは…である。まあ、ボート部には入部しなかったのだが…ちょっと記憶が重なり、楽しく読める一冊だった。ちなみに、私は応援団だった。
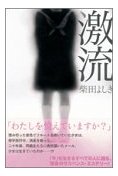 著者:柴田よしき
著者:柴田よしき
出版:徳間書店
初版:2005.10.31.
紹介:20年前。中学校の修学旅行中に行方不明となった少女の名でメールが届いた。
「私をおぼえていますか? 冬葉」修学旅行の班のメンバーの周囲で起こる嫌がらせ・ストーカー。誰が何のために、メールを送っているのか?
埋もれていた記憶のかけらが、探し出した事件の真相とは?
かなり分厚い本。しかも上下二弾組。けれども、面白くて一気に読めました。卒業して20年、それぞれが大人になり、各々の人生を送っている。
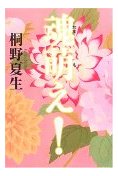 読んだ日:2006.06.04.
読んだ日:2006.06.04.
著者:桐野夏生
出版:毎日新聞社
初版:2005.04.25.
紹介:63歳の夫が心臓麻痺で急死した。それまで家に寄り付かなかった息子が海外から妻子もちで戻り、家を出て行った娘も帰ってくる。混乱の中でそれぞれの思惑がぶつかり、更に、思いもかけなかった、夫の愛人の出現。今までの自分の人生はなんだったのか?これからどうしたらいいのか?還暦を前にして、悩みゆれる心。私だったらどうする?誰だって、家だけは大丈夫!と思っているに違いないのだ。
結婚して専業主婦・二人の子供は成人して、夫は定年退職。これからゆったりとした老後を二人で迎えるつもりでいた…って、普通にある設定だけに、ドキッとさせられる。殺人事件が起きない変わりに、隣の家でありそうな?いや、どの家でも起こりそうな問題をはらんでいるので、そこに引っかかってしまう。
しかし、女はだんだん逞しくなっていくもの。ラストも、年齢を重ねた大人たちがしたたかに生きている様子が描かれていて、まだまだ人生先が長いと、予見されるのだった。
この本。若い人が読んでも、今一ピンとこないだろうなぁ。
 読んだ日:2006.05.28.
読んだ日:2006.05.28.
著者:石田衣良
出版:集英社
初版:2005.12.20
紹介:神楽坂の高層マンションの住人に光を当てる。
人がうらやむようなステキなマンションだが、そこに住む人々はそれぞれに悩みや問題を抱えている。
ルームシェアの相手に期待を込めた(空を分ける)不感症の妻に変化が訪れる(魔法の寝室)マンションを買おうと思い立った35歳直前独身女性(いばらの城)ニートの息子を抱える居場所のない父親(ホームシアター)63歳の恋愛(落ち葉炊き)これを愛人と呼ぶのだろうか。彼のために朗読をする部屋に住む女(本のある部屋)浮気を繰り返す純子の夢に出てくる男は?(夢の中の男)望んで生まれた子どもと仕事の間で追い詰められる(十七ヶ月)仕事の疲れを癒すのはマッサージ師の指(指の楽園)DVに苦しむ(愛がいない部屋)
そのマンションに暮らす人々の抱える様々な事情。ステキな高層マンションといえば、ちょっと住んでみたい様な憧れの気持ちがあるのだが・・・・そこに暮らす人々のちょっと辛い恋愛話が10編
めかぶのキャンペーンに応募したら特製図書カードが当たりました。
やっぱり、送らなくちゃあたらないもんね。
というわけで、またせっせとあれこれキャンペーンに応募しようと、思うのでした~。
しかし、この図書カードの図柄。バッチリめかぶが書いてある~
娘が見に行く予定だったオペラ。部活の練習を休めなくて、行けなくなってしまった。
せっかくなので、バイトを休みにして、夫婦で見に行くことにした。車で30分もあれば着くし~
初めてのオペラだけど、隣の区の文化会館だし、そんなに敷居は高くない。
きのうの夜。「ドン・ジョバンニ」の内容をネットでチェックして予習しておいた。
日本人が演じるオペラがどんなものなのか?
なかなか面白かったです。
急に夏がやってきた。
物は腐りやすくなり、カビも心配で困った季節がやってくる。
と思っていたら・・・・
夜中午前1:30。キッチンにアリ!あれ~どこから入ってくるんだろう?
真夜中のアリ退治となった。
餌になりそうなゴミ箱を外に出して・・・殺虫剤は・・・バタバタ
朝からゴミ箱を片付けて、洗って干して~
仕事帰りにアリ退治の薬を買って…アリの巣はどこだ???
これから暑くなると、ますます活動が活発になるだろうな。やだな~。
 著者:梨木香歩
著者:梨木香歩
出版:新潮社
初版:2005.08.30.
紹介:家に伝わる「ぬかどこ」がヒトを生み出す。かってに人がでてきては困るので、「ぬかどこ」を捨ててしまおう…と思わずに、故郷の島に戻そうと旅に出る話なのです。
こう書いてしまうと、何なんだ?と思ってしまいますが、実はそうなんですね。
家とか、幼少のときの生い立ち・呪縛にとらわれて、気づかないうちにどこかで屈折して生きてきた人間が、島に渡り、自分のルーツをたどることで、その呪縛を断ち切り、自分自身を取り戻す。
まあ、そこはわかるような気がするのですが、梨木さんのちょっと不思議な世界がなんだかとんでもないところへ広がって、特に間に挟まっている挿話がまあ、沼の話なんだけど、細胞分裂を繰り返していくあたりが具体的だけど象徴的で分かりにくくて、けっこうヘトヘトでした。
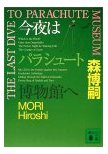 著者:森博嗣
著者:森博嗣
出版:講談社文庫
初版:2004.03.15.
紹介:N大学医学部に在籍する小鳥遊練無は、構内で出会った風変わりなお嬢様に誘われて「ぶるぶる人形を追跡する会」に参加した。大学に出没する踊る紙人形を観察し、謎を解こうというのだが……。不可思議な謎と魅力的な謎解きに満ちた「ぶるぶる人形にうってつけの夜」ほか、魅惑の7編(裏表紙より引用)
萌絵ちゃんと犀川先生がでてくるかと思えば、練無もでてくる。シリーズのサイドストーリー。なるほど、ココで「フランソワ」が登場したわけだ。
