 著者:森博嗣
著者:森博嗣
出版:講談社
初版:2006.05.09.
紹介:
山吹早月と加部谷恵美が乗車していた、東京発中部国際空港行きの高速バスがジャックされた。犯行グループは、都市部に爆弾を仕掛けたという犯行声明を出していた。
乗客名簿には《εに誓って》という名前の謎の団体客が。
《Φは壊れたね》から続く不可思議な事件の連鎖とを解く鍵を西之園萌絵らは見出すことができるのか?(裏表紙より引用)
えええ?そうだったの?うーむそうかぁ~
しかし、これって真賀田四季だっけ?これとどう関係してくるんだ?
 前作が面白かったので、ぜひみたいと思って行って来ました。
前作が面白かったので、ぜひみたいと思って行って来ました。
前作はひとつで完結していた感じでしたが、今度のは完全に「続き」がありましたね。というか未完でした。まだみていない人は、もう一度前作を見て復習してから行きましょう~
善と悪・敵と味方が入れ替わり、それぞれの利害で動くので思わず笑ってしまいます。
早く続きがみたい~という感じでした。
それから、エンドロールは最後まで見ましょうね。

東急田園都市線「桜新町」に降りると、そこにサザエさん通りがある。あたりは、そこここにサザエさんのキャラクターが描かれ、思わず足を止めてしまう。
この日、時間があったので、なかなか足を伸ばせなかった長谷川町子美術館に行ってみた。ちょうど夏休みで↑のアニメ展をやっていた。むかーしのサザエさんや、長谷川町子史など、なかなか興味深くみてきた。今度は収蔵品展の時に言ってみたいと思う。
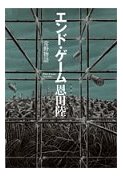 著者:恩田陸
著者:恩田陸
出版:集英社
初版:2006.01.10.
紹介:失踪した父と意識が戻らない母。二人の結婚は許されないものだったという。そして、自分の能力に気づかずにいた時子は、母の足取りを追う。そこには自分も知らなかった、不思議な世界が広がっていた。
コメント:常野の人々の能力って何だっけ?しまう?裏返す?「あれ」って?洗濯屋って?
「光の帝国」「蒲公英草子」とそこまでは良かったとして、「エンド・ゲーム」で何??っと思ってしまった。うーん。何のバトルゲームなんだ?
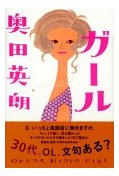 著者:奥田英朗
著者:奥田英朗
出版:講談社
初版:2006.01.20.
紹介:30代・仕事を持つ女性が、仕事とプライベートの間で揺れ動く短編5作。
ヒロくん:女性課長に抜擢された聖子。男尊女卑の意識が抜けない年上の部下の対応に苦慮するが…ありのままの自分を受け止めてくれるヒロくんに癒される。
マンション:友人のマンション購入に刺激され、マンションを購入を検討するが、お気に入りの物件のために海外旅行や観劇・お食事・おしゃれを我慢するか?家庭を持った男たちとの不思議な連帯感。自分らしく生きるためにとった選択とは?
ガール:いつまでも若いつもりでいても、周りは素通りして行くようになる。見えてくる現実と現実が見えていないような先輩OLの間で、自分の身の置き場に迷う30代。
ワーキングマザー:離婚して子供を育てている。しかし、仕事は仕事。仕事と子供とどちらも頑張ろうとする母親を見て子供は何を思うのか?
ひと踊り:ひとまわり年下の新人社員の教育係になった容子。しかも相手は女性なら誰でも足を止めるほどのイケメンである。年甲斐もなく新人に夢中になった容子は、群がる女たちから、新人を守ろうと周囲をガードするが…
女30代。結婚しててもしていなくても、子供がいてもいなくても、仕事をしていてもいなくても、それぞれ悩みは大きく深い。
だけど、どれも読んだ後、ちょっと幸せな気分になる。

著者:辻仁成
出版:幻冬舎
初版:2006.03.15.
紹介:男性の視点から書かれた、孔枝泳さんとの競作といえばいいのだろう。
日本人の感性の方が、ストレートに感情を理解できる。思いが一本で迷いがないのが分かりやすいせいかもしれない。
「冷静と情熱のあいだ」を思い起こす。
 著者:孔枝泳
著者:孔枝泳
出版:幻冬舎
初版:2006.03.15.
紹介:韓国から日本に留学に来た「紅」は日本人と恋に落ちる。しかし、韓国と日本の歴史上の悲しい事実と相互の認識のズレが、二人の間に溝を作る。耐えられなくなった「紅」は、恋を諦め韓国に帰るのだが、恋の呪縛から解かれることなく7年の歳月が過ぎる。日本人作家として突然目の前に現れた「潤吾」。封印された愛はどこへ行くのか?
コメント:日本と韓国の間には様々な問題がある。このラブストーリーを通して、ふだん私(たぶん平均的な日本人だと思う)が意識しないで見過ごしてきた歴史問題にライトを当てられた気がする。その点はとても興味深く読んだ。
しかし、それ以外のラブストーリー的観点からいうと、どうも「紅」に感情移入できなかったのでした。
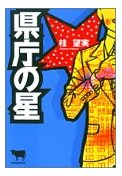 著者:桂望実
著者:桂望実
出版:小学館
初版:2005.09.20.
紹介:上級公務員試験で入庁したエリート県庁職員が、1年間の民間研修を体験する。配属先は活気のないスーパー。しかもパートの女性の下に配属され、マニュアルも指導も行われないまま売り場に出される。自分のやり方に自信満々の「県庁さん」は役所の効率的と考えるノウハウを持って、スーパーの体質を変えようと孤軍奮闘するが……。
去年、映画化されて、気になっていた作品。原作の登場人物は映画とは変わっているので、また違うサブストーリーがあるようだが、とても魅力的な人物がたくさん登場する。県庁さんが少しずつ変わっていき、それと共にスーパーも、周りの人も変わって行く様子は、気分がスッキリする。役所も変わらなきゃなぁ…と、ちょっとと思ったしだいです。DVDになったらぜひみよう!
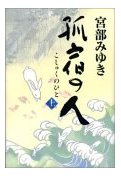 著者:宮部みゆき
著者:宮部みゆき
出版:新人物往来社
初版:2005.6.21.
紹介:
妻子と家臣を殺した、加賀様が江戸から丸海藩へやってくる。流人か鬼か、疫災か、刺客を招き雷神を招く。平和な丸海の人々は混乱の中に放り込まれる。
おびえる人々とその影に隠れ暗躍するのは誰なのか?流行病の原因は?様々な人々のそれぞれの思惑を巻き込んで、丸海が壊れて行く。藩ををつぶさずに江戸への体面を保ちつつ、事態を収拾させる手立てはあるのか?
幸薄く幼いほうと、加賀様がわずかな救いで、加賀様の深い悲しみが胸にしみる。本当の鬼はどこに隠れているのか?
宮部みゆきの時代物。話の中にグイグイ引きこまれ、下巻は1日で読み終えてしまいました。
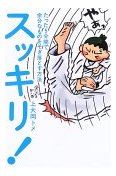 著者:上大岡 トメ
著者:上大岡 トメ
出版:幻冬舎
初版:2005.11.10.
紹介:たった5分間で、余分なものをそぎ落とす方法
「着ない服、はかない靴に無駄な家賃は払わない。」「散らかっているものは、とりあえず拾う」「古いタオルは思い切って処分する」…ウーン。まさに私のこと?
その他にも、なるほど~と思う事もちょこっとあったな。
でもまあ、私はけっこう「スッキリ!」してる方だなぁ。と思ったりして
